いきなり自慢で申し訳ないが、私はGun誌の第1回ビデオコンテストにて、佳作入選をしている。銃にのめりこんでまだ間はなかったが、スポンジのように知識を吸収した結果だと思う。それでも、第一線で現場に出ている人達に比べれば屁以下である。今では私も素人同然、こんな私にできることは、こうやってブログでくっちゃべるだけだ。
映画や映像作品におけるガンアクションは、大別するとリアル派とスタイル派に分かれる。リアル派とは、その名の通りリアルさを追求し、シューティングスタイルや銃の選別、設定、効果音から特殊効果に至る全ての過程において、現実にあるかのようなアクションを追求するものである。
スタイル派とは(私が勝手に命名したのだが)、リアルさはある程度量るものの基本的には除外し、ガンアクションのかっこよさや派手さに注目して演出するものである。
リアル派の代表格としては、マイケル・マンが挙げられるだろう。まさかこの記事の閲覧者にマイアミバイスを知らない者はいるまい。劇中では毎回いろんな銃が登場し、しかも無意味に出てくるわけではなく、ちゃんと理由づけて登場させるところがガンマニア垂涎である。実際、ある回では本物のシューターが殺し屋として登場、ガバメントの早撃ちをやってのけた。演技の方はさほどではなかったが、なかなか不気味な役どころであった。
一方、スタイル派の代表格としては、香港ノワールが挙げられるだろう。そう、ツイ・ハークでありジョン・ウーであり、チョウ・ユンファである。「男たちの挽歌」のあのシーンは、今でも目を瞑ると瞼に焼き付いているくらいに鮮烈であった。
リアル派が見れば、あんな使い方するなよと一蹴しそうだが(私も実は同意見だったが)、あれほどかっこいいシーンはどこの映画にもなかった。やがてそのスタイルは全世界のアクション映画に取り入れられ、今ではスタンダードアクションの一つになっている。
どっちがかっこいいかというのは愚問である。演出というのは適材適所であり、役者やプロットによっても変えるものである。重要なのは、如何に監督の演出意図に沿うか、そして如何に観客を魅了できるか、この二点である。
一時期流行した銃を寝かせて撃つスタイル、あれは例えば右バリケードでオートを撃つ場合、排莢された薬莢がバリケードに跳ね返って危ないので銃を寝かせるわけだが、見た目がかっこいいので普通のスタンドシューティングでも使われることが多い。リアル派の意見としては、あれはシングルハンドでリコイルの制御に無理がかかるので、小口径かライトロードでないと命中精度はかなり劣る。しかし、やはり見た目はかっこいいのでよく見かける。
リアル派の演出としては出番のなさそうなアクションだが、ギャングやチンピラなどにこの撃たせ方をすると、使えないこともない。しかし、連射はやめたほうがいいだろう。プロップガンとはいえ、リコイルが不自然になるからだ。
リアルを追求して袋小路に入ったり、スタイルを追求してあさっての方向(日活アクションとか)に行ってしまってはだめだ。プロットやキャラクターを見極めて、自分なりのスタンスでやってみよう。
月: 2004年7月
東京進出
大阪で売れてきた芸人がよく口にする言葉である。明石家さんま、ダウンタウン、ナインティナイン、まさに大活躍である。東京で一旗揚げようという、その意気込みはよくわかる。しかし、少し立ち止まって考えて欲しい。彼らが、東京へ行って失った物があることを。
東京へ進出した芸人は、確かにテレビによく出ている。そこで、彼らはどんな仕事をしているのだろうか。番組の司会である。そこに、芸の場はない。己の芸を生かすことはできるだろうが、ネタを見せて笑いを取っているのではない。
それは、芸人としてどうだろうか。
東京進出で金儲けはできるだろうが、己の芸が未熟であれば、ただのタレントに成り下がってしまうのだ。そうまでして、東京へ出る意味があるのだろうか。
東京は野球でいうメジャーに例えられる。大阪芸人は、いくら腕があっても東京ではルーキーである。しかし、東京にメジャーに例えるほどの笑いがあるだろうか。むしろ笑いに関して言えば、大阪のほうがメジャーである。東京はただ、情報発信の中心であり、人口が多いだけなのである。笑いを知らない、流行に流されやすい客の前で、己の芸が向上するはずがない。東京で芸を潰してきた芸人は、決して少なくないはずだ。
芸人の本分は、舞台に立ち、客の前でネタを披露して笑いをとる。多少シチュエーションは変わっても、ネタで笑いをとるのが芸人の本分ではないのだろうか。
ようやく最近、ゴングショー形式も含めてネタ見せができる番組が増えてきた。大阪を出て、東京へ行くのは構わない。が、どこへ出ようとも、ネタで勝負して欲しい。キャラクターやルックスではなく、ネタで勝負して欲しい。
特に、千原兄弟とハリガネロック。東京のクソみたいな芸人に負けてるぞ。何をしとんねん。もっと頑張らんかい。
コロッケうどん
と聞いて、みなさんはどんな食べ物を想像するだろうか。コロッケでできたうどん、コロッケの形をしたうどん、コロッケみたいなうどん。いやいや申し訳ない、ただコロッケが乗っているだけの普通のうどんである。
たぶん見たことも聞いたこともないだろう。日本全国どこの店にいってもそんなメニューにはお目にかからないと思う。私がそれを知ったのは、学生食堂であった。
当時、我が大阪芸術大学には、大きな二つの食堂、それぞれ第一、第二という食堂があった。第一食堂(以下一食)は、主に音楽系やデザイン系など、割とスカした学生が集まり、第二食堂(以下二食)には、我々映像系や写真系などオタク連中がたむろする、住み分けのできた食堂であった。
そのコロッケうどんは、一食のメニューであった。普段ずっと二食で食事をとっている私にとって、一食で食べることはおろか、中へ入ることさえ滅多になかった。しかも、学生の昼食にまずうどんは選ばない。がっつりした定食か、カレーや丼ものがほとんどである。
しかしある日、何かでたまたま一食で打ち合わせをしたとき、小腹が空いたので何か食べることになった。食券の販売機に違和感のあるメニューがある。「コロッケうどん?」私は思わず声に出して呟いたほどだ。確か160円くらいだったと思う。腹の好き具合もぴったりだったので、食券を買ってカウンターのおばちゃんに渡した。
それはすぐにやってきた。何のことはない、コロッケが乗ったうどんである。席に着いて、しばらく眺めてからコロッケを箸で突いた。
揚げ立てだったのだろうか、コロッケは軽く音を立ててうどんつゆにしみていった。一口うどんをすすって、コロッケを少し割ってみた。衣と中の具が、うどんつゆの中に溶けていく。コロッケがだんだんつゆを吸ってふやけてくる。つゆを吸ったコロッケを一口食べた。
うまい。コロッケが溶けたうどんつゆも、絶妙な味具合である。うどんと揚げ物といえば、きつねうどんも似たようなものであるから、食べ合わせとして違和感はないと思う。こうして、私とコロッケうどんは出会った。
それからというもの、一食で食事するときは、腹具合にかかわらずコロッケうどんだった。一人暮らしをしていたときも、実家に戻った今でも機会があれば食べている。
みなさんもぜひ一度、お試しいただきたい。
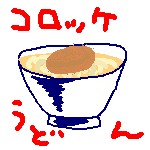
井上睦都実 「恋は水色」
ロンドンの音、というのが私にはわかる。洋楽はあまり聴かないが、イギリス出身のポップやロックバンドには、独特の音がある。それが、なんとなくわかったりする。それよりもっとよくわかるのは、ピチカートの音、である。
初めて彼女の曲を聴いたとき、インスト部分でそのピチカートの音が聞こえた。これは間違いないと思ってCDを買いにいくと、そこにはTokyo's Coolest Comboとあった。小西康陽が組んだ、ちょっとジャジィなインストユニットである。そういえば、何かの記事で女性ヴォーカルをプロデュースするようなことが書いていったが、それが彼女だった。
ヴィブラフォンをフィーチャーした清涼感溢れるサウンドと、彼女の明瞭な音程を刻むヴォーカルが合わさって、実に小気味よいサウンドに仕上がっている。セカンドチューンの「抱きしめたい」はシングルヴァージョンもあるのだが、リズムセクションがより重厚感を増していて気持ちいい。そういえば、小西氏はベース引きだったなと改めて感じる。アシッドジャズのフレーヴァーが加味されているのだろうか。
現在も睦都実嬢は健在であるが、大病を患われていたらしく、最近復帰された。西日本限定情報だが、NTT西日本のCMで、その姿が見られる。浴衣姿もあでやかな、あのさおりちゃんである。これには私も驚いた。あの浴衣美人は誰だろうと思っていたのだが、まさか睦都実嬢だったとは。
CMが見られない地域の方も、ネットで探して見ていただきたい。ブログだからといって、親切にリンクを貼ると思ったら大きな間違いである(`へ´)
井上睦都実 公式ウェブサイト http://www.2ikstudio.com/
SRCL2486 SONYRECORDS 19921021
王将 外環富田林店
大阪芸術大学は、大阪の南はずれにある。普通に生活していては、まず通らないような僻地にある。そこに大学がなければ、たぶん誰も行かないだろう。だが、そこで過ごした四年間は、たぶん人生で一番楽しかった時期ではないかと思う。まさに青春の日々であった。
寮生活は、それまでの生活にないものばかりであった。友人と夜通し遊ぶなど、中高生ではできないことだった(今は違うが)。家族中心の生活から、自分中心の生活に移った。はめを外すということはなかったが、もっと遊んでおけばよかったかなとも思う。
年間制作でつるんだ連中と、よく飯を食いに行ったのがタイトルの王将である。週に一度、年間制作の授業が終わって、男四人を一台の車に押し込んで(しかもトヨタのセラ!)、昼飯といえば王将だった。
大体決まって頼むのが、豚肉とキャベツのみそ炒めと鶏肉の香味揚げである。豚肉とキャベツのみそ炒めは、まあいわばホイコーロウであるが、甘めのみそダレが好みに合った。鶏肉の香味揚げは、確か梅肉のあん仕立てのソースがかかっていたような感じだった。酸味が効いてて癖になる味である。もちろん、一品ものはそれぞれ頼んだものをみんなでつつき合う。私はこれにチャーハンだったが、他の連中には天津飯が人気だった。
授業の話、映画の話、バイトの話、女の話。話は尽きなかった。食事した後は、ゲームセンターかバッティングセンターかボウリング場に行くというのがお決まりのコースだった。
毎週のように行くものだから、ある日いつも同じ女の子の店員が注文を取りに来るのに気づいた。まあまあかわいい程度の子だったが、注文票に「ようこ」と書いてあったのを見つけて、次から「ようこちゃんとこ行こうや」が王将へ行く隠語となった。ま、別にそれ以外大した話はない。今でも働いていたらびっくりするが。
8月1日、富田林では日本一の花火大会がある。私は一度だけ見たことがあるが、あれは花火ではない。火薬の量は小規模な紛争並みである。一度見れば、二十年は花火を見なくても済むだろう。それほどすごい花火大会である。付近一帯の道路を全て封鎖して行われるので、近鉄電車で。1km以上離れてご覧になることをお薦めする。
具島直子 「miss G.」
一目惚れならぬ、一耳惚れというのをよくやる。例えば、カーラジオから流れてくる曲や、CDショップの適当な視聴機で聴いた曲、具島直子の場合は、テレビの天気予報だった。夕方帯の情報番組の天気予報で、どうしようもなく切ない、耳に残ってしまう曲が流れていた。それがアルバムのトップチューン「Melody」であった。
具島直子の曲は、時間と場合を選ぶ。午前中はだめだ。天気のいい日もだめだ。深夜もだめだ。夕暮れ時、今日という日が暮れていく黄昏時、できれば車の中でこれからちょっと訳ありのところへ出掛けていく、というのがベストだろう。
以前、友人と車で遠出したとき、さあこれから地元を離れるぞと高速に乗っていて、ふと山下達郎が流れた。今までそれほど気にも留めていなかった彼の音楽が、その時突然、私の心に入ってきたのだ。音楽は、ただ漫然と聴いているだけでなく、そのシチュエーションで思いがけない効果があるということを知った瞬間である。
具島直子のサウンドもそうだ。時間やシチュエーションを合わせたときに、彼女の歌は何百倍にもなって心に響いてくる。そういう聴く人に入り込むようなサウンドを、大事にしたいと思う。
TOCT9459 EASTWORLD 19960605
映画の三師匠 #3 アンドレイ・タルコフスキー
高校時代、のべつまくなしに映画を観ていた私にとって、名画座の存在は非常にありがたかった。京都の北のほう、繁華街から遠く離れたところに京一会館という劇場があった。京都の映画フリークなら、その名を知らぬ者はいないだろう。たった500円で三本も映画が観られるのである。高校生の少ない小遣いでは、月にロードショー1、2本観るのが限界だが、京一会館はだいたい二週間交代で映画を掛けてくれていた。ただし、たまに成人映画があるので日を間違えるとえらいことになる。
私はそこで、ほんとにいろんな映画を観た。小津も寺山も大島も、チャップリンもヒッチコックも、果てはエイゼンシュテインまで。寺山修司の二本立てなどは、私がモラトリアム期だったらヤバかったかもしれない。
その中で、私が最も感銘を受け、なおかつ強烈な衝撃を与えてくれたのが、タルコフスキーの「ストーカー」である。
今でこそ小規模な配給会社が世界に埋もれているマイナーな名画を紹介してくれるが、当時はアメリカのメジャーな映画しか劇場には掛からず、ヨーロッパの映画はレイトショーや劇場以外での公開が多かった。「ストーカー」は、京大の近くにある日本イタリア京都会館で観た。今となっては、どうやってその封切情報を手に入れたのか定かではないが、おそらく新聞の地方欄にでも載っていたのだろう。そこは、劇場というより、上映会のノリに等しかった。学校の教室の半分くらいの部屋に、三十人分ほどの椅子が並べられていた。平日の夜だったので、私は学校帰りに制服のまま出掛けていった。
冒頭のシーンで、それがただの映画ではないことがわかった。プロットを追うのも忘れさせるほどの映像が、私を眩ませた。これほど美しい映画を、私は観たことがない。プロットが難解で追えない分、その映像が強烈に焼き付いた。
映画監督になろうとか、映画を撮ろうとかはっきりと思ったり口に出したことはないが、例えばビデオカメラやスチールカメラを覗くとき、私の脳裏の奥深くには、いつもタルコフスキーの映像が焼き付いている。
歌って踊る、ガンアクションたっぷりの美しい映画。きっと私が撮るのはそんな映画だ。カンヌは獲れないだろうが、「シベリア超特急」には勝てるかもしれない。