サンライズリアルロボット派の雄、高橋良輔が指揮を執った作品。植民星の独立運動という政治的なストーリーを取り入れ、粗製濫造な作品が多い中で75話という一大叙事詩を謳い上げたのがダグラムである。
コンバットアーマーはずんぐりむっくりで余りリアル感はなかったが、ストーリーは実にリアルであった。政治を扱ったアニメは、後にも先にもダグラムだけであろう。
メカとしては、さほど人気のないコンバットアーマーだが、地上用多脚メカを輩出したのは功績である。中でも、私が一番好きなのが、六本足のデザートガンナーである。
デザートの名が示すように、砂漠専用に開発されたものだ。人間が砂の上を歩くと足を取られるように、二脚メカも砂に弱い。第15話「ダグラム砂に沈む」の回を中心に、砂に弱い二本足のダグラムを六本足のデザートガンナーが攻め立てていくのだ。
この”二本足は砂に弱い”という言葉に、当時の私はいたく感銘を受けた。ガンダム全盛時代、水中用や砂漠用のモビルスーツが半ば無理矢理設定されていたが、デザートガンナーほど理屈に合ったメカはないだろう。二本足は砂に弱い、だから足を増やして機動性を確保する。またデザートガンナーの砂上での動きが速いこと速いこと。結果的にはダグラムに敗れ去るわけだが、戦術上ではデザートガンナーのほうが有利だったはずだ。
ガンダムに比べれば、コンバットアーマーにさほど魅力がなかったのは否めない。それでも番組が一年半も続いたのは、スポンサーがバンダイではなくタカラであったからかもしれない。もしバンダイであれば、ダグラムは未完の大器としてアニメファンの恨みを買っていたに違いない。
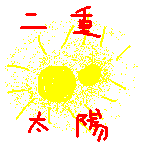
カテゴリー: アニメ
超時空要塞マクロス
舞台設定をスタジオぬえが担当しているだけあって、SF考証は他のアニメの追随を許さない。ハードな物語になるかと思いきや、美樹本晴彦の耽美キャラがゆるゆるとした感を生み出すも、板野サーカスと呼ばれるスピーディなメカ作画が引き締める。
そんな絶妙なバランスが素晴らしいマクロスだったが、唯一許せない点がある。作画の海外発注だ。
作画や仕上げの海外発注を本格的にし始めたのは、このマクロスあたりからではないだろうか。今でこそ当たり前で、アニメ制作の分業化を担う重要な役割になったが、当時はまだ作画のレベルが悪く、日本との差は歴然であった。このマクロスは、更に輪をかけて酷かった。
マクロスは、前半こそ日本で製作されていたが、中盤あたりからスタープロという海外の制作プロが担当した。これが劣悪極まりないものだった。
動画はちゃんと割ってない、デッサンはできてない、パースはむちゃくちゃ、色パカ(彩色の塗り間違いで色がパカパカ変わって見えることから)はあちこちにあるわで、とても番組として成立していなかった。まさに不良品である。楽しみに観ているこっちはたまらない。
特に私が憤慨しているのは、ミリアというキャラクターが好きだったのだが、彼女の登場シーンは大概スタープロ担当の回であって、番組ではロクな彼女を観たことがないのだ。大事なアップショットでは、両目があさっての方向を向いている始末。
確かに、予算が充分に行き渡らず、動画の枚数をケチることもあるだろうが、秒1コマで動いているのを観たときはさすがに諦めた。もはやアニメーションではない。紙芝居である。
アニメ製作は手間の割に予算が少なく、宮崎アニメやジャパニメーションで潤っている今も現場は厳しい。確かに当時の海外発注は最悪だったが、今は日本を超えるほどの作画力を持つようになった。彼らなしで、今のムーブメントはなかったと言っても過言ではないだろう。
日本はどんどん追い越される時代になってきたのかもしれない。
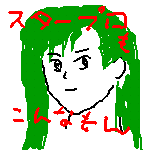
冒険王クラッチ
アメリカの古いアニメである。学生時代に地方U局で放送していた、15分程度の番組である。
そんな番組をなぜブログで取り上げるのかというと、一度観たら忘れられないアニメだからである。動く映像をお見せできないのは残念だが(たぶんビデオに録ってどっかにある)、文末のURLを参考にしていただきたい。
アニメーションにもいろんな手法があるが、この冒険王クラッチは、口だけが実写合成されているのだ。これが実に気持ち悪い。しかもなぜかその実写の唇は男女キャラ問わず赤く、一層気持ち悪さを引き立てている。
口元だけが実写なものだから、アップショットが多用され、引きの絵は普通のアニメになっている。しかも大きな動きがほとんどなく、動いているのは艶かしい唇だけである。
確かに、セリフと口パクを合わせることは必要かも知れないが、それが枷になって肝心のアニメーションができていない。しかし、視聴者には強烈な印象を残した作品である。
どっかにあるビデオを探してみよう。
クラッチカーゴ資料館 http://ppgcom.gooside.com/sands/clutchcargo.html
YouTubeにて映像発見。
ルパン三世・カリオストロの城
何か一つだけ、好きなアニメ作品を挙げるとすると、ガンダムでもなく、ボトムズでもなく、劇場版パトレイバー2でもなく、攻殻機動隊S.A.Cでもなく、私はこの作品を挙げる。連続投稿すると2ちゃんで糾弾される某映画レビューサイトにも書いたが、十年二十年、五十年百年経っても、日本のどこかで鑑賞されている作品だと思う。
確かにガンダムは好きだし、ガンダムがなければ今の私の半分は構成されていないと思うが、作品としては実に不完全なものである。不完全であるから我々ファンが付け入る隙がいっぱいあり、そこへいろんな思い入れが重なって、未だに熱が冷めないのだろう。
カリ城は、作品としては完璧である。完璧であるから、我々が付け入る隙は全くない。ということは、我々は完全に一視聴者としてだけこの作品に接することができる。作品世界に没頭できるからこそ、時代を経て再視聴したとき、以前と自分の視点が変わっていたり、新たな発見ができたりする。
毎日観るとさすがに飽きると思う。だが、一年二年経つと、観たいなあという気持ちが沸いてくる。ルパンという人気作品のバイアスを考慮しても、この作品は日本アニメ界の最高傑作だと言えるだろう。
宮崎監督がどんな映画祭で賞を獲ろうが、時代を超えて鑑賞される作品はカリ城をおいて他にない。それは、22世紀になればわかるだろう。
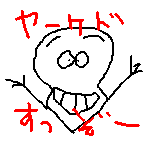
カウボーイビバップ
オープニングを観て、私は確信した。これはすごい作品になると。私にとっても、アニメ界にとっても、である。
一話完結のスタイルは、プロットに程よいテンポを与え、軽妙洒脱なセリフと切れのいいアクションが華を添える。キャラクターも細部まで作り込まれていて、決して難解でない適度な伏線も随所に張られている。
声優陣も素晴らしい。特にスパイク役の山寺宏一は、三枚目の外見とは裏腹に、男の私が聞いてもセクシーでかっこいい声を持っている。スパイクと山ちゃんがイコールだとわかったとき、正直いろんな意味でショックだった。今では洋画の吹き替えも多数こなし、第一線での活躍が目覚しい。
久々に出てきたハイクオリティのアニメだったが、唯一惜しむらくは映画である。劇場用作品がもっと盛り上がっていれば、ビバップは今でも熱く語られていたはずだ。
ビバップのアイデンティティでもあるストーリーのテンポが、劇場用の尺で間延びしてしまい、ビート感が全く欠けていたのだ。オムニバスでもよかったかもしれない。
だが、テレビシリーズ全26話の完成度は非常に高く、筆舌に尽くし難い。未見の方はネットでも視聴できるのでぜひ。「へヴィメタルクイーン」「ガニメデ慕情」「道化師の鎮魂歌」あたりが私のオススメである。

銀河漂流バイファム
ガンダムがロボットアニメの主権を握って以降、勧善懲悪というコンセプトは薄れ、ヒーローという言葉も影を潜めていた。リアルロボットの時代である。
そのリアルロボットの中核を担っていたのが、言うまでもない日本サンライズ(当時)である。富野喜幸を筆頭に、高橋良輔や神田武幸らが次々とリアルロボットアニメを世に送り出していった。銀河漂流バイファムは、その絶頂期にあった作品と言えよう。
オープニングから度肝を抜かれる。全編英語詞である。もちろん、テレビアニメ史上初である。キャラクターデザインは芦田豊雄が担当、作画もスタジオライブが中心に手掛け、リアルなストーリーの中にもほのぼのとしたキャラクターで、視聴者に親近感を与えていた。
作品解説は他に譲るとして、私が特筆したいのはシップクルーの会話である。例えば、宇宙船が宇宙港から発進するシーン。他のアニメなら2、30秒で済ますところを、バイファムでは数分かけて細かく描写している。
クルーの会話、コンピュータの操作などが実に細かく設定されていて、当時観ていた私もちんぷんかんぷんながら、その緊迫した雰囲気だけは感じていた。
もちろん、そういった設定は劇中で説明されることはないが、それがかえってリアルさを引き立て、バイファムの物語世界を構築していった。
そのリアルなセリフがあればこそ、ラストシーンの緊張と緩和が成立し、私を含めた視聴者の涙を誘うのである。サンライズのロボットもので最終回に感動したのは、後にも先にもこのバイファムだけであった。
バイファムファンサイト http://www.v-gene.com/
スタッフ
監督:神田武幸
脚本:星山博之
作画:芦田豊雄
1983.10.21~1984.9.8

侍ジャイアンツ
私は阪神ファンである。プロ野球において、巨人というチームの存在こそが球界再編を阻む根本原因だと思っている。しかし、侍ジャイアンツは別格であった。この番組を観ているときだけは、自分が阪神ファンだということを忘れて熱中していたように思う。
巨人の星とは違い、この作品だけはアンチ巨人ファンも楽しみに観ていたと思う。それは番場蛮の豪快で爽快なキャラクター描写によるものだろう。現実のプロ野球界をベースにしながら、荒唐無稽とも思える大胆なシナリオ展開によって、視聴者を一気に現実から物語世界へ引き込む。叙事詩的な巨人の星に比べ、ミュージカルのような侍ジャイアンツ。
なんといっても魅力はあの魔球である。ハイジャンプ魔球に始まり、エビ投げハイジャンプ、大回転魔球、分身魔球縦・横、そして最後のミラクルボール。非現実的と言ってしまえばそれまでだが、毎回わくわくしながら観ていた数少ないアニメである。
それらの魔球を破ろうと、眉月、大砲、ウルフ・チーフら数々のライバル達が凌ぎを削った。魔球誕生の経緯にわくわくし、その魔球を破ろうとするライバル達の奮闘にわくわくする。番組を観ているときだけは、物語の世界にどっぷりと浸かり、現実のプロ野球はどこかにいってしまう。
でっかいクジラを腹の中から突き破るはずが、結局は飲み込まれてしまったわけだが、最終回、ワールドシリーズで投げたまさに奇跡のミラクルボール。メジャーを打ち取った番場蛮に、私も心からおめでとうと言ったものだ。
魔球の特訓風景がいじめにつながるとかいう実にくだらない(アホか)理由で再放送ができないようだが、DVDも出ているのでこの作品を知らない方はぜひ観ていただきたい。
余談だが、分身魔球以外は全てボークになるそうな。
