テレビ神奈川は、地方のUHF局であるにもかかわらず、非常にクオリティの高い音楽番組を作り続けている。その中に、ミュージックトマトジャパンというプロモーションビデオを流す番組があった。PVに興味を持った私はその番組を録り続け、今では膨大な資料の山となっている(そろそろ機材揃えてディスク化したい)。
手持ちのCDも少なくなってきたので、そのMTJから私がインスパイアされたミュージシャンをブログってみようと思う。
ヘビメタクイーンという称号は、その華奢な風貌からは容易に想像できないが、彼女のパワフルなシャウトと類い稀なる美貌は、まさにヘビメタクイーンにふさわしいと言えよう。
自らも作詞作曲をこなし、80年代中盤から90年代前半にかけて、精力的にアルバムを発表し続けた。私が初めてPVを観たのは、「MISTY LADY」「HEART LINE」の辺りである。それほどヘビメタは好きでもなかったし、映像もライブビデオからのピックアップなど当たり障りのない内容で、曲の印象もそれほどではなかった。彼女の魅力は、「BLUE REVOLUTION」で知ることとなる。
初の芝居仕立てのPVで、ブルーに統一された色調が彼女のクールさを引き立て、そこにあのシャウトが絡む。だが、これ以降、彼女は次第にポップ路線へと転向し、派手なシャウトはやや陰を潜めていく。
他に好きな曲は「CALL MY LUCK」「CRIME OF LOVE」だが、「CRIME OF LOVE」は渋く切ないバラードで、まだ健在な頃のシャウトが涙を誘う名曲である。ぜひ一度聴いていただきたい。
先日、デビュー20周年を迎えた浜田麻里、現在も精力的に活動中である。
浜田麻里ファンサイト http://www004.upp.so-net.ne.jp/marihamada/
月: 2004年9月
侍ジャイアンツ
私は阪神ファンである。プロ野球において、巨人というチームの存在こそが球界再編を阻む根本原因だと思っている。しかし、侍ジャイアンツは別格であった。この番組を観ているときだけは、自分が阪神ファンだということを忘れて熱中していたように思う。
巨人の星とは違い、この作品だけはアンチ巨人ファンも楽しみに観ていたと思う。それは番場蛮の豪快で爽快なキャラクター描写によるものだろう。現実のプロ野球界をベースにしながら、荒唐無稽とも思える大胆なシナリオ展開によって、視聴者を一気に現実から物語世界へ引き込む。叙事詩的な巨人の星に比べ、ミュージカルのような侍ジャイアンツ。
なんといっても魅力はあの魔球である。ハイジャンプ魔球に始まり、エビ投げハイジャンプ、大回転魔球、分身魔球縦・横、そして最後のミラクルボール。非現実的と言ってしまえばそれまでだが、毎回わくわくしながら観ていた数少ないアニメである。
それらの魔球を破ろうと、眉月、大砲、ウルフ・チーフら数々のライバル達が凌ぎを削った。魔球誕生の経緯にわくわくし、その魔球を破ろうとするライバル達の奮闘にわくわくする。番組を観ているときだけは、物語の世界にどっぷりと浸かり、現実のプロ野球はどこかにいってしまう。
でっかいクジラを腹の中から突き破るはずが、結局は飲み込まれてしまったわけだが、最終回、ワールドシリーズで投げたまさに奇跡のミラクルボール。メジャーを打ち取った番場蛮に、私も心からおめでとうと言ったものだ。
魔球の特訓風景がいじめにつながるとかいう実にくだらない(アホか)理由で再放送ができないようだが、DVDも出ているのでこの作品を知らない方はぜひ観ていただきたい。
余談だが、分身魔球以外は全てボークになるそうな。

ナベツネ
憎まれっ子世にはばかるというが、昔から世の中は悪い奴ほど得をするようになっていたのだろう。
それにしても、ナベツネ周辺のブレインは優秀である。オリンピック直前という絶妙なタイミングで、自浄を装った手前ミソな裏金問題を露呈させ、引責辞任という形で表舞台から見事に消し去った。
これで正々堂々と球界再編の敵役から逃れ、あとは悠々自適の隠居生活である。あーやれやれといった感じだろう。件の学生は、さしずめスケープゴートといったところか。かわいそうに。
私は、読売巨人軍の改革なくしてプロ野球界の改革はないと思っている。巨人戦がないと他球団が儲からないという状況を、誰一人として疑問に思わないのはどういうことだろうか。
近年のプロ野球は、全て巨人中心に動いてきた。その諸悪の根源がナベツネであり、奴が消えた今こそ、腐った球界を再生できるチャンスである。
選手のストライキ、新球団、交流試合。最もプロ野球に必要なのは、富の分配である。それはテレビの放映権料であり、ドラフト制度の見直しである。巨人偏重の風潮がある限り、何をやってもだめだろう。
強いものが勝つというのがスポーツである。しかし、金や権力で得た勝利であってはいけないのだ。
妖怪人間ベム
オープニングはジャズである。あんなクールなアニメソングは、ビバップかベムかというくらいである。話の内容は別に意味でもっとクールだ。
この作品、実は韓国製であることが最近わかった。今ではかなりの日本製アニメが韓国や中国で製作されているが、こんな古い時期から既に共同製作が始まっていたのだ。
言われてみれば、キャラクターや動きなど、同時期の他のアニメと比べてあまり類似点がないような気もしないではない。
当時は日韓関係も厳しく、反日感情は今の比ではなかっただろうが、両国の友好のために共同製作が企画されたそうだ。
残念ながら放映当時はスポ根もの全盛であまり人気が出ず、ベム以降の共同製作は解消された。しかし、再放送が繰り返されるうちに人気に火が付き、今では日本を代表するアニメの一つになっている。
折しも、高度経済成長期のツケが公害となって日本中を苦しめていた時代、妖怪人間ベムはこれからの社会のあり方について問題提起し、警鐘を鳴らしたのだ。
「早く人間になりたい」
番組では彼らのその思いは叶わなかったが、今ならその願いもきっと叶うことだろう。
参考資料 http://f1.aaacafe.ne.jp/~monokuro/bem.htm
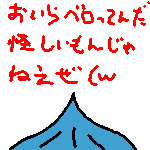
魔法のプリンセスミンキーモモ
実に衝撃的な作品であった。ゴーショーグンのノリを引き継いだハッピーな魔法少女アニメは、悪ノリしすぎて本当に予告編でレミー島田を出してみたり、ミンキナーサというゴーショーグン紛いのロボットを出してみたり、やりたい放題みたいな印象があった。観てる側はそれで充分楽しかったのだが、それが衝撃のラストを引き立てる伏線とは思いたくない。
魔法少女もので、最終回に主人公が死ぬ作品は、後にも先にもミンキーモモだけであろう。
モモは、夢の国フェナリナーサから、人々に夢と希望を与えるためにやってきた。しかし、人々は夢も希望も持とうとはしない。だんだん魔力が失われていくモモ。そして、遂に魔法が消え、彼女は不慮の事故で死んでしまう。こんな悲しいラストが許されていいのだろうか。
主人公の死もそうだが、なんでもできるはずの魔法でさえ、結局は現実の人間に対して何もできなかったという、現代社会に対する皮肉が心に刺さる。モモを死なせたのは、実は我々の心だったのだと。
スポンサーの気まぐれで打ち切りと延長が同時に決まったため、最終回以降も第二部的に話が続いたのはせめてのも救いである。
90年代に続編が製作されたが、こちらもハッピーエンドにはならなかった。実に辛いアニメである。
キャスト
モモ:小山茉美
シンドブック:田の中勇
モチャー:木藤玲子
ピピル:三田ゆう子
パパ:納谷六朗
ママ:土井美加
王様:増岡弘
王妃様:塚田恵美子
スタッフ
監督:湯山邦彦
脚本:首藤剛志
キャラクターデザイン:芦田豊雄
作画:わたなべひろし
放映日時:1982.3.18~1983.5.26

戦国魔神ゴーショーグン
私にとっては禁断のカテゴリーとも言えるアニメーション。手始めに葦プロあたりから攻めたいと思う。
葦プロと言えば、首藤剛志、湯山邦彦、いのまたむつみである(書いてて懐かしー)。気持ち的には小山茉美も入れたいところだ。私自身、ゴーショーグンはかなりはまった覚えがある。徳間書店刊で発売された首藤氏のオリジナル小説まで買っていたのだから、そのはまりようがわかると思う。
破滅志向に陥って大失敗した前作のバルディオスの反省もあって、ゴーショーグンは脳天気なくらいのネアカでスタートした。タイムボカンシリーズ並みの善悪キャラの掛け合いが絶妙で、各キャラクターが物語の中で実に生き生きとしていた。正直、ストーリーなどどうでもいい。ストーリーはキャラクターを見せる筋書きに過ぎないのだ。
しかし、このキャラクターありきの作風が、スポンサーのへそを曲げてしまった。おもちゃが売れないのだ。テレビ番組は、スポンサーの商品を売るために作られるのが大前提であり、それに叶わなかった番組は問答無用で打ち切られる。あのガンダムでさえそうなのだ。ある意味、ソーラレイより恐ろしい。メディアミックスの今なら、一本調子なスポンサーで番組が潰れることもなかっただろう。
スポンサーの眼鏡には適わなかったが、アニメファンはがっちりとゴーショーグンを受け入れた。その証拠に、現在もなおゲームなどでゴーショーグンの名を見かけることがある。ゴーショーグンを見て育った大人達の、せめてもの恩返しだと私は思う。
ところで、なぜゴーショーグンが”戦国魔神”なのか、ご存知の方はご一報いただけるとありがたい。
小説版ゴーショーグン 参考URL http://www2.vc-net.ne.jp/~nausicaa/goshogun/novels.html
キャスト
北条真吾:鈴置洋孝
キリー・ギャグレー:田中秀幸
レミー島田:小山茉美
真田ケン太:松岡洋子
レオナルド・メディチ・ブンドル:塩沢兼人
スーグニ・カットナル:木原正二郎
ヤッター・ラ・ケルナグール:郷里大輔
(タツノコネーミング・・・)
スタッフ
監督:湯山邦彦
脚本:首藤剛志
作画:田中保
放映日時:1981.7.3~1981.12.28

韓流に流されるテレビ局は溺れてしまえ
日韓交流を妨げるつもりは毛頭ないし、ドラマに感化されてロケ地を巡ることを非難するつもりもない。私も、東京へ行く機会があれば「探偵物語」のロケ地へ行ってみたいくらいだ。
しかし、柳の下のドジョウを躍起になって探しまくっているテレビ局の姿勢だけは、許すことができない。そう思ったのは、フジテレビの「クイズ・ヘキサゴン」を観てからだ。
その日、番組の回答者はいわゆる一発屋の人達を集めていた。メンツからして、ほとんど紳介師匠の身内(円広志と桑名正博と高原兄て・・・)であるが、こっちとしてはそのほうがトークも冴えるので面白いだろうと観ていた。しかし、この日は番組中に冬ソナの未公開シーンを流すという知らせが何回もあった。別に気にも留めずに観ていたのだが、それは8時40分頃のことだった。
ある回答者が問題を指定すると、それは冬のソナタに関する問題であった。そこで、その未公開シーンが流れたわけである。
よーく考えていただきたい。
視聴率稼ぎで未公開シーンを流しているのは明らかである。8時40分頃といえば、水戸黄門なら印籠が出る時間だ。
しかし、普段の回答者は問題をランダムに選んでいる。ということは、この時間にこの問題を選ぶということを、予め決め打ちしていたのだ。
これがテレビのやり方である。一応スタッフの名前を列挙しておくが、一番悪いのは編成のバカ共である。
■プロデューサー・演出
神原 孝(バラエティー制作センター)
■プロデューサー
西 雅史(D:COMPLEX)
■ディレクター
池田よしひろ(D:COMPLEX)
奥村達哉(D:COMPLEX)
武田直也(D:COMPLEX)
■制作
フジテレビバラエティ制作センター
■制作協力
D:COMPLEX
面白いクイズ番組だったんだけどね。